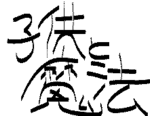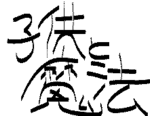オーボエ2本が5度や4度で並行して単調なメロディーを聴かせます。
低音楽器も伴奏もありません。拍子も分かりません。不安定な感じの、か弱い出だしです。
か弱さに輪を掛けるかのように、コントラバスという超低音楽器が
何と、ハーモニックスという特殊な弾き方で、かすれたような高音を奏でます。
1分ほどで、部屋の真ん中にポツンといる少年が小さな声で歌い始めます。
「宿題なんていやだ。散歩に行きたい。お菓子を食べたい。」
何だか、出だしの寂しげな音楽が、
少年の満たされない心をそのまま表しているように感じませんか?
オペラでは、オーケストラは単に歌の伴奏というだけでなく、
登場人物の気持ちを音楽で表すこともあります。
風景や状況を表すこともあります。
例えば嵐の場面では、音楽が嵐を表すのです。
(この作品には嵐は出てきません。)
さて、お話しの方は、
少年の不満が段々高まってきます。
動物をいじめたいとか、あげくにはお母さんを困らせてやりたいとか言い出します。
声は段々高くなっていきますが、
オーケストラの音楽はさみしいままです。
少年の心が満たされていないということを音楽が表しているように感じられます。

すると突然クラリネットやバスーンが綺麗(きれい)な和音を鳴らします。
トップへ 次へ→